日本テニス協会 普及推進本部副本部長 今井茂樹氏
「テニピンでテニスのミライを創る」の講義を聞いた感想
「テニピン」は本当によく考えられたスポーツ。
講義を聞いて一番初めに印象に残ったことは、テニピンというスポーツは本当によく考えられたスポーツであることです。小学生にラケットを扱うことが難しい。ラケットを集めることも難しい。上手な子だけが輝いてしまう。テニスの授業を一般化することは難しかったようです。
それを、ラケットの代わりに、手で打つような形に用具を改良したこと、道具を段ボールで作れるようにしたこと、ダブルスにしたこと、交互に打たなくてはいけないこと、4回ラリーをしたのちでないと得点できないルールとしたこと、などの工夫で解消しています。

テニピンを普及するためにあらゆる努力をされたこと。
国立大学付属小への配属という幸運はあったものの、テニピンへの取り組みを新聞へ投稿、教育雑誌へ投稿、松岡修造氏との対談の申し込み、テニス協会へのPRなど、ありとあらゆる手段を使ってPR活動など行い普及をされてきました。その行動力が素晴らしいものを感じました。
当初松岡修造氏はラケットを使わないことなどに対し、テニスではないのではないかなど、懐疑的な発言をされていたようですが、今井氏はテニピンがラケット操作の向上をもたらすことを証明する研究成果を持ち、再度説明するなどし、現在は松岡修造氏も認め、応援してくれているとのことです。
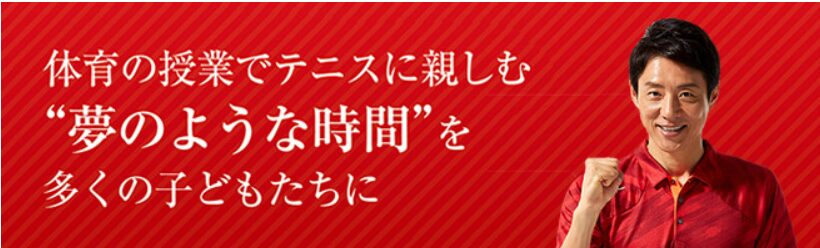
学校現場に普及させるためには楽しく体育に親しむ、運動を好きになる、そのような視点をどれだけもてるか
テニスの強化のため、バドミントンの強化のため、普及のためにテニピンを教育現場に普及させなければ、、、等という発想ではいつまでたっても普及は行えないということ。学校現場の体育、楽しく運動することにテニピンがどれだけ役に立てるかという発想で普及を進めているということです。
1,個が輝く
2,状況を判断する力
3,戦略を練る力
4,問題を解決する力
5,成功も失敗も自分ごと
バドミントンに置き換えてみるとどうすればよいか?
テニスとバドミントンの違いはバウンドして打ち返してよいか、ノーバウンドで打ち返すかの違いにあると思います。
どうしたら優しさを確保してノーバウンドで打ち合うことが実現できるか?
1,コートを狭くする
2,風船など、ボールを工夫する
3,コート内の人数を多くする
などの工夫が必要ではないかと思います。
また、教育現場でバドミントンはどういった教育効果あるか?
テニピンを参考にすると
1,個が輝く・・・・・・・・当てはまる
2,状況を判断する力・・・・当てはまる
3,戦略を練る力・・・・・・当てはまる
4,問題を解決する力・・・・当てはまる
5,成功も失敗も自分ごと・・当てはまる
6,道具を上手く扱う(巧みさ)
バドミントンも工夫次第では教育現場で楽しく、体育として役立つスポーツの一つとして採用される可能性はあるのではないかと思います。ただし、バドミントンのそのままではやはり、専門的すぎたり、費用的な面でも難しいのではないかと感じます。
参考にしたページ
日本テニス協会HP



コメント